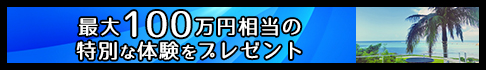分譲も賃貸も経験。行き着いたのは好きな街・清澄白河で「店舗併用住宅」
コーヒーとアートの街として知られる清澄白河(東京都江東区)。この街の一角に今年2021年8月、酒屋「いまでや 清澄白河」が誕生しました。店のコンセプトは「はじめの100本」。お酒に詳しくない人でも、日本各地の日本酒やワインなどに詳しくなっていけるという、お酒のセレクトショップです。10月22日から「角打ち」(酒を酒屋の一角で立ち呑みすること)もできるようになりました。

住宅街の一角にできた「いまでや 清澄白河」(写真撮影/相馬ミナ)

日本酒やワインを知るための「はじめの100本」がコンセプト(写真撮影/相馬ミナ)

「これはどんなお酒?」と手に取りやすく、会話もうまれやすい仕掛けがしてある(写真撮影/相馬ミナ)
店舗付き住宅の場合、オーナーが自宅で商売をする、または、不動産会社にテナント誘致を任せることが多いのですが、今回の家はそれとはまったく事情が異なります。この家の所有者は、広告代理店に勤務し、「若者研究」などで知られる小島雄一郎さん。自身で酒店を口説いて誘致し、「自分の家の1階に大好きな酒屋が入る」という酒飲みの夢のような家を建てた、というのがそのあらましです。とはいえ、いきなり店舗併用住宅という結論に至ったのではなく、実は「賃貸or購入」という、30代の住まいの「命題」について考え抜いた結果だったといいます。
「もともと、清澄白河近くの賃貸住宅で暮らしていましたが、コロナ騒動前は年間100日ほど出張があって、自宅にいないのに家賃を支払うという状況だったんです。だったら、買うにしても借りるにしても、『家』に“働いて”もらったほうがいいんじゃない?というのがそもそものはじまりなんです」と話します。

キッチンからリビングをのぞむ。どこを切りとってもスタイリッシュ(写真撮影/相馬ミナ)
ただ、賃貸物件であっても、分譲物件であっても、集合住宅ではAirbnbなど民泊の時間貸し、部屋の貸し出しは、規約で禁じられていることが多いもの。「集合住宅で家に働いてもらう」のは、すぐに厳しいと気がついたそうです。
「次に考えたのが中古物件+リノベです。ただ、下町で流通する中古物件は、建ぺい率(敷地面積に対する建物の建築面積)がオーバーしているなど、現在の法律だと違法建築だったり、既存不適格だったりするため、住宅ローンが使えないこともあるようです。そのため、結果として新築の注文住宅、しかも店舗併用住宅という発想に至りました」といいます。こうして小島さんの「借りるor買う」からはじまった住宅問題は、「大家になって稼ぐ家をつくる」という判断になったのだといいます。

小島さん宅の間取り1、2階(画像提供/須藤剛建築設計事務所)

小島さん宅の間取り3、PH階(画像提供/須藤剛建築設計事務所)
建築、食、酒、アートなどに触れる暮らし。家を建てたことで、「自分の文化度」が上がった
ただ、東京の人気エリアで、土地を買って、新築で店舗併用住宅を建てるとなれば、金額的にも大きな決断になることには違いありません。
「土地を買ってこの建物を建てたのですが、建物の建築面積は90平米程度、建物は3階建てで、2階と3階、屋上が住まいになります。東京都内の新築マンション価格はあがる一方なので、結果としては新築マンションを買ったのと同程度の価格帯におさまりました」といいます。毎月の住宅ローン収支でいうと、家賃収入を返済額に充てれば、ご自身で支払う返済額は賃貸に住んでいたころの賃料の半額程度といいます。ただ、自宅にはサウナがあったり、屋上でバーベキューや流しそうめんができたりと、暮らしの満足度、充実度は比較になりません。

リビングを横から。つるされたグリーン&ギターが素敵(写真撮影/相馬ミナ)

2階の寝室&仕事スペース。手持ちの和箪笥もなじんでいます(写真撮影/相馬ミナ)

2階にはサウナも! 建築家もサウナ好きだったそう(写真撮影/相馬ミナ)

屋上。目の前は寺社で、遮るものがなく、大きな空が広がる(写真撮影/相馬ミナ)
「建築家と建てた家なので、インテリアをはじめ、好みのテイストで統一できていて、暮らしの満足度は比べ物になりません。ただ、電気配線工事の依頼や各種手続きなどは自分ですべてやらなくてはいけなくて、手間はかかりました。新築マンションや賃貸だと、ぜんぶセットアップされているので、決められた手続きをしていけば暮らしがはじめられますが、注文住宅なので一つひとつ自分がやらなくてはいけない。大変でしたが、家を建てるなかで、建築やインテリア、食、地域やコミュニティへの理解など、自分の暮らしの『文化度』があがった気がします」と家を建てた経験を振り返ります。

(写真撮影/相馬ミナ)
また、家について考えていたこの1年は、コロナ禍でリモートワークが導入され、働き方や家の価値、街との関わり方について考えることも増えたといいます。
「在宅時間が増え、家や街のことをより考えるようになり、単なる収入ではなく、大家として自分にも、街や地域にもよい影響があったらいいなと考えるようになりました。当初、店舗部分はワークシェアスペースやレンタルスペースも考えましたが、コロナ禍で先が見えないし、カフェやギャラリーはすでにある店と競合する……と考えを整理していき、最終的に酒屋、しかも角打ちもできる店がよいだろうと。そこまで考えたあとで、自分で酒店を見学してまわり、誘致することにしたんです」といいます。
大家として土地や不動産を所有し、テナントや店子の管理はすべて不動産管理会社にまかせて「収入を得るだけ」という人はたくさんいますが、企画から開発まで、自分で考え、行動に移すのはさすがとしかいいようがありません。
勝ち馬に乗るのではなく、街を盛り上げた結果としての「資産」に
とはいえ、自宅の1階を店にするには、やはり覚悟と手間が必要だったといいます。
「自宅の一部で店をはじめるので、街や周辺住民との関わり方、当事者意識がまったく異なります。周辺にも、はじめる前もあいさつをしに行きました。清澄白河は、下町ということもあり、飲食店や商店、町内会などの横のつながりがあります。地域との関わりは、今までの賃貸や分譲マンションでは考えられないほど、深くなりましたね」と小島さん。

夕方、暗くなりはじめて明かりが灯ると、独特の風情が漂う(写真撮影/相馬ミナ)

無事に開店。近所の人がふらりと立ち寄っていくのがおもしろい(写真撮影/相馬ミナ)
いわゆる不動産を所有することで、「資産を形成する」「所得を得る」だけということは、したくなかったといいます。
「清澄白河は今、盛り上がっている街ですが、だからといって何をやってもうまくいくわけではありません。自分が当事者として地域や街を盛り上げていった結果として、地価や資産が守られたらいいなとは思いますが、勝ち馬に乗って売り抜けるようなことは考えていませんでした」といいます。自分が当事者として地域に関わり、地元愛が盛り上がった結果として、資産が維持できたらいいというのは、不動産本来のあり方といえるでしょう。
今回、小島さんが声をかけたことで、住宅街の一角に店を出すことになった、株式会社いまでやの専務取締役の小倉あづささんは、どのように考えているのでしょうか。

小島さんもこの1年でだいぶお酒に詳しくなったとか(写真撮影/相馬ミナ)

左がいまでやの小倉さん、右が小島さん。大家と店子って本来、こんな感じだったのでしょうか(写真撮影/相馬ミナ)
「昨年の秋ごろでしょうか、突然、出店しないかというメールが会社に来て、おもしろそうな人だから会ってみようというのが、はじまりでしたね。当初は店を出すつもりはなくて、2回目に会ったときも出店する意向はなかったのですが、小島さんが家賃を含めて、本気で関わろうという姿勢を見せてくれたんですよね。そこではじめて覚悟や思いを感じたというか。何度も場を設けて、弊社の社員にはない知識や経験をもらって……を繰り返していくうちに、結局、出店することになりました」と1年を振り返ります。

小島さんがはじめにIMADEYAさんに送ったプレゼン資料(画像提供/小島雄一郎さん)
ただ、この1年はお酒や外食産業にとって、先の見通せないつらい時期でもありました。緊急事態宣言が続き、お酒を飲み交わす場はすっかり精彩を欠いていたように思います。
「弊社は酒を販売するだけでなく、飲食店にも卸しているのですが、まさかこんなに長くコロナ禍が続くとは思ってなかったな」とぐちる小倉さん。
「ご近所の人は暖かくて、店の工事をしていると『今度は何屋ができるの?酒屋?楽しみだね』と言ってもらったり、『酒器も売っているんだね、今度来るから』と言ってもらえたり。期待度や関心度を実感していました」(小倉さん)
一方で、家飲み需要が高まっているという手応えもあり、小島さんと小倉さんとで店のコンセプト「はじめの100本」の完成度を高めていったそう。そして、デジタルを活用しつつ、お酒が好きな人も、すでに詳しい人も楽しめる仕掛けをして、今年8月、無事、お店がオープンとなりました。

「この酒をオススメする人の名前、顔、理由」がおもしろい。全部飲みたい(写真撮影/相馬ミナ)

グラスにいれると色がわかって、またきれい(写真撮影/相馬ミナ)

お酒って話ながら選ぶのがおもしろいんですよね。貴重な交流の場に(写真撮影/相馬ミナ)
「お酒は川の流れと同じで、常に人の暮らしに寄り添ってきたんです。今回、感染症対策で、飲食店で呑むのは難しい時期が続きましたが、だからこそ家では、美味しいお酒を飲んでほしいという思いは強くなりました。それと、美味しいものはなぜ美味しいのか、知識があるともっと楽しくなる。また、お酒の知識は人との会話で得るのが一番、記憶に残るんです。角打ちは、そういうお酒の楽しさを学ぶ場であり、サロンにもなる。人とお酒とが盛り上がる、豊かな場所にしていけたらいいですよね」と小倉さん。
「『お店なんて、よくできたね』と言われるんですが、3階建てのうち1階を自動車の車庫にしている家はよくありますよね。それと同じ感覚で、車庫部分にお店を誘致してきただけ。会社員でも、十分、ありえる方法だと思いますよ」と小島さん。1階に車庫があれば交流は生まれませんが、酒屋があることで、お客さんや地域と交流がうまれます。小島さん自身は、まだ家を所有している感覚はないといいますが、暮らしや地域に根ざしている感覚があるといいます。これも家の完成までに、多くの人とやりとりしたからこそかもしれません。
単に住む街、眠る街から、商いの当事者として関わる街へ。関わりが増えれば、手間や煩わしさも増えることでしょう。でも、それ以上に豊かに、得るものはきっとあるはず。買うor借りる、の発想を超えて、新しい暮らし方へ。すでに流れは変わっているのかもしれません。

静かに光る「いまでや」の看板。新しい光ですね(写真撮影/相馬ミナ)