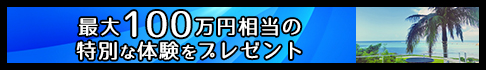宿泊客以外も利用できるカフェを併設。開かれた宿が街歩きの起点に
長野県松本市の浅間温泉は、飛鳥時代から約1300年続くとされ、温泉街から車で10分の距離に松本城があり、安曇野や上高地、白鳥など信州全域への観光拠点になっている。いま、時代の変化に置いて行かれ、歴史があっても廃れていく温泉街が後を絶たないが、浅間温泉街も例外ではない。城下町の奥座敷という恵まれたロケーションにありながら、全盛期に比べ、温泉街を歩く人の姿は減少していた。
そこで、温泉街再興の起爆剤として2018年3月に始まったのが、貞享3(1686年)創業の歴史を持つ老舗旅館「小柳」の再生プロジェクト「松本十帖」だった。ホテル単体の再建ではなく、温泉街を含む「エリアリノベーションのきっかけ」になることを目指した画期的な取り組みだ。

江戸時代には松本城のお殿様が通い、明治時代には与謝野晶子や竹久夢二ら多くの文人に愛された浅間温泉。昭和の時代には温泉街に芸者さんも多かった(画像提供/自遊人)

路地の坂を歩けば温泉街に来た旅情が催してくる(画像提供/自遊人)
4年の歳月をかけて2021年5月に誕生した複合施設「松本十帖」は、宿と街の関係を深める新しいモデルとして注目を集めている。もともと老舗旅館「小柳」が建っていた敷地内に、「HOTEL松本本箱」と以前の名前を冠したまったく新しい「HOTEL小柳」がオープン。ホテル内には、ブックストア、ベーカリー、レストランなどがあり、宿泊者以外も利用できるように入口を4か所設けて、地域に閉じていた旅館を「解放」。2軒のカフェ「Cafeおやきとコーヒー」「哲学と甘いもの。」は、“温泉街を人々が回遊すること”をイメージして、あえて敷地外につくった。

敷地内の小道を歩いていくと宿泊棟の「HOTEL松本本箱」が現れる(画像提供/自遊人)

小柳旅館の大浴場を本屋に改装したブックストア松本本箱。選書は日本を代表するブックディレクターの幅允孝(はばよしたか)さん率いる『BACH』や、日本出版販売の選書チーム「YOURS BOOK STORE」による(画像提供/自遊人)

「HOTEL小柳」1階にある「浅間温泉商店」は、良質な生活雑貨や食品を取りそろえている(画像提供/自遊人)

「松本十帖」は、さまざまな施設が集まった総称。敷地内の「HOTEL松本本箱」のなかにブックストア松本本箱があり、「HOTEL小柳」にはベーカリーやレストランなどがある。2軒のカフェはホテルから150mほど離れた敷地外にある(画像提供/自遊人)
古民家を借り受けて改装した「Cafeおやきとコーヒー」は、ホテルのレセプションを兼ねている。そもそもホテル敷地内には駐車場がない。宿泊者の駐車場はホテルまで徒歩2、3分のカフェ「Cafeおやきとコーヒー」の横にあるのだ。宿泊者は、まず、カフェでチェックインし、おやきとコーヒーのウェルカムサービスをいただいてから、温泉街を歩いて、歴史ある温泉街を訪れたという気持ちを高めながら、ホテルへ向かう。ホテルに着くと、Barを兼ねたフロントでは、スタッフが温泉街の成り立ちや文化を紹介してくれる。

「Cafeおやきとコーヒー」の建物は、かつては芸者さん専用の浴場であり、また置屋(休憩室)でもあった(画像提供/自遊人)

宿泊者には、チェックイン手続き後、2階のカフェスペースでウェルカムスイーツのおやきと飲み物がふるまわれる(画像提供/自遊人)
ホテルから温泉街全体へ波及させ、地域活性化を目指す「松本十帖」は完全な民間プロジェクト。一般的に公的資金を投入して行うようなプロジェクトを引き受けた株式会社自遊人代表取締役でクリエイティブディレクターの岩佐十良(いわさ・とおる)さんに、プロジェクトにかける想いを伺った。
「私が思い描くのは、メインストリートに人があふれるほどにぎわう浅間温泉街の姿。『松本十帖』が、その呼び水になれば。『地域に開かれた宿』と注目されていますが、私にとって地域に開かれた宿が当たり前という感覚です。そもそも温泉街は、街歩きを楽しむ場所としても発展してきました。しかし、昭和30年代以降、観光バスでやってきて宿の中で楽しむ団体旅行が主流になり、街なかにあったラーメン屋やカラオケ、バーまでも施設内に取り込んで、大型化していきました。宿泊施設の中で完結するようになった結果、温泉街が廃れてしまったのです。でも、そういう時代は終わりました。宿に来てもらうだけでなく街に出てもらう。『松本十帖』は、双方向から仕掛けをつくっています」(岩佐さん)

「小柳旅館」の再生プロジェクトは、岩佐さんにとって民間企業として何ができるのかの挑戦でもあった。設備投資が莫大な旅館運営を行うのは並大抵の苦労ではないという(画像提供/自遊人)
また食べたい! もっと知りたい! 旅の心残りがリピートのきっかけ
温泉街に人を呼び戻すには、まずは、「行ってみたい」と思わせる宿がいる。雑誌「自遊人」を発行する出版社の経営者である岩佐さんは、新潟県大沢山温泉の「里山十帖」など地域の歴史や文化を体験・体感でき、ライフスタイルを提案する複合施設としてのホテルをプロデュース、そして自ら経営してきた。「HOTEL松本本箱」「HOTEL小柳」の設計を依頼したのは、注目の建築家、谷尻誠氏と吉田愛氏が率いるサポーズ デザイン オフィスと、長坂常氏が代表を務めるスキーマ建築計画など。サポーズ デザイン オフィスが「HOTEL松本本箱」を手掛け、スキーマ建築計画が敷地内の「小柳之湯」や「浅間温泉商店」「哲学と甘いもの。」などを手掛けた。小柳旅館解体時に現れた鉄筋コンクリートの躯体やもともとの内装を活かしながら、洗練されたホテルに生まれ変わった。

「HOTEL松本本箱」最上階のスイートルームからは、北アルプスの山並みが見える(画像提供/自遊人)

ホテルから徒歩3分ほどの距離にあるカフェ「哲学と甘いもの。」(画像提供/自遊人)

難解な哲学の本に疲れたらスイーツを(画像提供/自遊人)
ユニークなのは、昔からある地域住民のコミュニティ「湯仲間」で管理し利用する共同浴場を、あえて「松本十帖」の中に復活させたこと。「Cafeおやきとコーヒー」の2階席の階下には、湯仲間しか入れない共同浴場「睦の湯」がある。地域住民しか入浴できない温泉を、観光客が出入りする「松本十帖」に取り入れた狙いはどこにあるのだろうか。
「従来の考え方では、観光客が入れないんだったら意味がないじゃないかと思われるかもしれませんが、私はこういった見えない文化も観光資源だと思っているんです。『睦の湯』など、浅間温泉各所にある共同浴場には、地元のタンクトップ姿のおじさんが、四六時中温泉街を歩いて温泉に入りに来ます。これこそが、生活に根付いた温泉街の姿ですよね。観光客も『入れない風呂があるなんて面白そうだ』と感じてくれます。そこで、観光客と湯仲間のおじさんの間に『どんなお風呂なんですか』『めちゃくちゃいい湯だよ』といったような会話が生まれるかもしれません」(岩佐さん)
それが、岩佐さんが「生活観光」と呼んでいる地域の風土・文化・歴史を体感できる新しい旅。「睦の湯」を通して、偶発的な会話が生まれるように「松本十帖」という場所がデザインされているのだ。観光客用には、「松本十帖」の敷地内に「小柳之湯」を用意している。設備は「睦の湯」と同じく、シャンプーやボディーソープはなく、脱衣所と半露天のシンプルな浴槽のみ。源泉かけ流しの小さな湯舟に浸かれば、生活の中に息づく温泉街を感じられる。

敷地の真ん中、正面入り口前に設けられた「小柳之湯」(画像提供/自遊人)

観光客は、「小柳之湯」で浅間温泉各所にある湯仲間専用の共同浴場を疑似体験できる(画像提供/自遊人)
ホテルにはリピーターも多いが、大きな理由は“食”にある。ホテルの夕食は、地域の「風土・文化・歴史」を表現した料理で、レストラン名は、「三六五+二(367)」。三六七(三六五+二)は信州をS字に流れる日本一の大河、千曲川(信濃川)の総延長が367kmであることに由来する。365日の風土と歴史、文化(+二)を感じてもらいたいという思いが込められている。食材は地場の野菜や千曲川・信濃川流域と日本海でとれた魚が中心。キャビアなどの豪華食材を使うことはなく、季節のものを厳選し、いつ来ても違う味に出会える。ほかに、1万冊を超える蔵書を誇るブックカフェ「松本本箱」のとりこになり、リピーターになる人もいる。料理と本で「また食べたい」「もっと知りたい」という「旅の心残り」を誘う。松本十帖は、コロナ禍による閉塞感からの解放にとどまらず、自分の感性を磨いたり、思考を整理したり、ポジティブな目的を持って訪れる人が多いそうだ。

夕食は『三六五+二(367)』『ALPS TABLE』ともにコース料理。いずれも地域の風土・文化・歴史を表現した「ローカルガストロノミー」がコンセプト(画像提供/自遊人)

公式サイトで「地味だけど滋味」と表現される料理が体に沁みる(画像提供/自遊人)
日常でも非日常でもない「異日常」へ もう一人の自分に会いに帰る旅
岩佐さんが手掛けたホテルを何度も訪ねている鈴木七沖さん(すずき・なおき、57歳・編集者)に魅せられる理由を伺った。25年間、本づくりに携わり、現在は映像制作も手掛けている鈴木さんは、神奈川県茅ケ崎市在住で、「箱根本箱」には6回、新潟の「里山十帖」には3回、「松本十帖」にはオープン直後に訪れている。「松本十帖」の敷地外のカフェでチェックインした鈴木さんは、細い温泉街の道を歩いて宿まで移動しながら、気持ちが整っていく感じがしたという。本をゆっくり読むため外出することは少ないが、温泉に入ったり、食事をしたりするのがいいリセットになる。

「箱根本箱」滞在中の鈴木さん。ホテルでは原稿を執筆したり、自身が制作した映画の編集を行うことも。「たくさんの本が装置になって新しい発想が生まれるんです」(画像提供/鈴木七沖さん)

里山十帖のイベントで話し合う岩佐さんと鈴木さん。同じ編集者として岩佐さんのものづくりのコンセプトに共感している(画像提供/鈴木七沖さん)
「僕の場合は、観光する目的ではなく、自分の考えを整理したり、発想力を豊かにするために宿泊しています。何回も通っている理由は、なんていうか、自分の‘‘残り香‘‘がする場所になっているからなんです」(鈴木さん)
‘‘残り香‘‘とは何かたずねると、鈴木さんは、「日常ではない場所にいるもう一人の自分」だと答える。
「『松本十帖』だけでなく岩佐さんの手掛けたホテルでは、日常ではなかなか出会えないもう一人の自分に出会えるんです。旅行に行くというより『帰る』という感覚。自分と対話できる時間と空間がたっぷりある。僕にとって魔法が生まれる場所です」
普通の観光であれば、南の島に行ってきれいな海で泳ぐなど非日常を楽しむのが目的だ。鈴木さんの体験は、日常でも非日常でもない「異日常」という表現がしっくりくる。鈴木さんは街づくりのオンラインサロンを運営しているが、「異日常」は二拠点生活の感覚に近いという。
「異日常は、日常では思いもよらないアイデアだったり、もう一つの感性だったりを気づかせてくれる場所という気がします。30年ぐらい前だとバックパックで海外の非日常に自分探しに出かける人が多かったですが、今は自分を探すより深める時代だと思うんです。誰もが一カ所から二カ所、異日常を持つ。日常とは違う自分が所属できる場所を持つ。そういう風に捉えると旅の面白みが増えるのではないでしょうか」
松本十帖の成功をみて「ぜひ出店したい」と「cafeおやきとコーヒー」の目の前におしゃれなパン屋さんができた。岩佐さんは、「浅間温泉街を起点に松本市内にいろんなマップマークが出てくれば、大きなうねりが起きる可能性がある」と期待を寄せる。宿から街に人の流れができれば、地域のファンになり、関係人口として関わる人も増えるはず。新しい旅の形には、人口減少問題解決の鍵となる地方再生の可能性が秘められている。